ベア君の市民後見見聞録
市民後見の理解のために
ベア君の市民後見見聞録のホームページへようこそ。
このホームべージは、市民後見活動の理解のためにつくられたものです。
市民後見制度は、認知症や知的・精神障碍者などで、福祉サービスの契約や預貯金の管理等が困難な人の権利や財産を保護し、支えるための制度です。
お知らせtopics

浦和フェスタにNPO市民後見センターさいたま参加
2月9日(日)午前10時〜午後3時30分までコムナーレ10階で開催された浦和フェスタに「NPO市民後見センターさいたま」は、参加しました
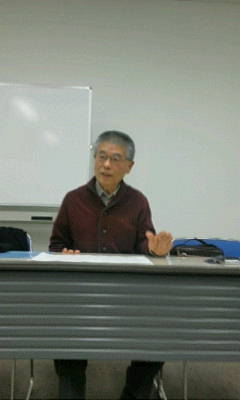
NPO市民後見センターさいたま12月学習会
2013年12月28日(土)午後5時から学習会が開催されました。コムナーレ10階会議室で飯塚理事を講師として3つの後見事例の報告がありました.

NPO市民後見センターさいたま終活フェアに参加
1月19日(日)午前11時から浦和コルソホールで相談会を開催しました。
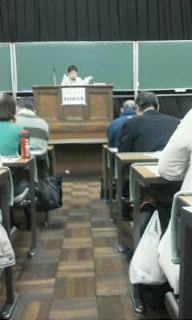
東京大学市民養成講座に参加
1月25日(土)、26日(日)に参加
浦和区わくわく浦和に参加(2月28日)
2月28日(日)午前10時〜午後3時30分までコムナーレ10階で開催されました。
10名のスタッフが参加し、後見相談コーナーを設置して対応しました。
熱心な相談が多く午後4時すぎても相談者がいました。
<
さいたま市・いきき長寿課に4つの提案・1つの問題敵
を文書で提出(1月14日)
1月14日(水)午前11時に4つの提案・1つの問題提起を文書で
提出した。
浦和区市民活動ネットワーク連絡会に参加(9月30日)
9月30日(水)午後1時30分〜コミュニティ活動コーナーで第4回交流部会・広報部会が開催されました。
市民後見センター8月セミナー参加(8月22日)
8月22日(土)午後1時30分〜南浦和コープブラザでセミナーが開催されました。
夢ロック第4回例会に参加(8月8日)
8月8日(土)午後4時〜午後6時までコムナーレ9階でセミナーが開催されました。
浦和区市民活動ネットワーク連絡会に参加(7月22日)
7月22日(水)午後1時30分〜ネット連絡会議さいたま市地域包括センター運営協議会に参加(7月17日)
7月17日午後2時30分〜さいたま市地域包括センター運営協議会が開催
されました。
浦和区わくわく浦和フェスタに参加
2月15日(日)午前10時〜。午後4時までさいたま市のコムナーレ10階で開催されました。
浦和区市民活動ネットワーク連絡会に出席
1月14日(水)午後1時30分〜。さいたま市浦和コミュニティセンターで開催されました。
浦和区市民活動ネットワーク連絡会に出席
1月14日(水)午後1時30分〜。さいたま市浦和コミュニティセンターで開催されました。
浦和区市民活動ネットワーク連絡会に出席
11月26日(水)午後1時30分〜。さいたま市役所内のコミュティ活動コーナーで開催されました。
また、12月10日わくわく浦和の案内パンフの発層業務に参加しました。
11月19日(水)午後2時〜4時まで。NIKKEIセミナーに出席
超高齢化社会における
医療と安心安全な長寿社会づくり
日経カンファレンスルームで開催されました。
10月22日(水)午後1時30分〜4時まで。浦和区市民活動ネットワーク連絡会に出席
さいたま市役所内のコミュティ活動コーナーで開催されました。
10月16日(水)午後1時〜2時まで。埼玉県庁を訪問
そこにあった資料には?
浦和区市民活動ネットワーク連絡会に出席
9月24日(水)午後1時30分〜4時まで。さいたま市役所内のコミュティ活動コーナーで開催されました。
浦和区市民活動ネットワーク連絡会に出席
8月27日(水)午後1時〜4時30分まで。さいたま市役所内のコミュティ活動コーナーでで開催されました。
学習会に参加
8月23日(土)午後1時〜3時までコムナーレ9階で開催されました。参加者は約30名、講師は渡辺オフィース代表の渡辺さんでした。
夢ロック研修会に参加
8月2日(土)午後2時〜さいたま市Sさん宅で開催されました。参加者10名で事例研究について報告・討議を熱心にしました。
浦和区市民活動ネットワーク連絡会に出席
月23日(水)午後1時30分〜午後4時30分までさいたま市役所内のコミュティ活動コーナーでで開催されました。
東京大学・市民後見人養成講座フォローアップ研修会に参加
7月5日(土)〜6日(日)午前9時30分〜午後4時30分まで東京大学本郷キャンパス工学部2号館213番教室で開催されました。
(写真は、工学部2号館前の案内看板)
 さいたま家庭裁判所訪問
さいたま家庭裁判所訪問
月13日(火)午前9時からさいたま家庭裁判所を訪問した。敷地内での写真撮影は、禁止とのことであった。

月20日(日)午後1時30分〜午後3時30分まで東京大学・市民後見人養成講座 第6期生履修証明書授与式に参加
東京大学本郷キャンパス法文2号館31番教室で履修証明書授与式がありました。
(写真は、東京大学正門)
東京大学・市民後見人養成講座に参加
3月21日(金)〜23日(日)午前9時30分〜午後4時30分まで東京大学本郷キャンパス法文2号館31番教室で開催されました。
(写真は、安田講堂)
コムナーレフェスタにNPO市民後見センターさいたま参加
3月1日(土)〜2日(日)午前10時〜午後4時コムナーレ9・10階で開催されました。
NPO市民後見センターさいたま2月学習会
2月22日(土)午後?時30分〜3時30分コムナーレ9階で開催されました。
講師は、井上副理事長の「介護離職をしなければならないかどうかの体験」、大塚さんの介護施設の選び方でした。